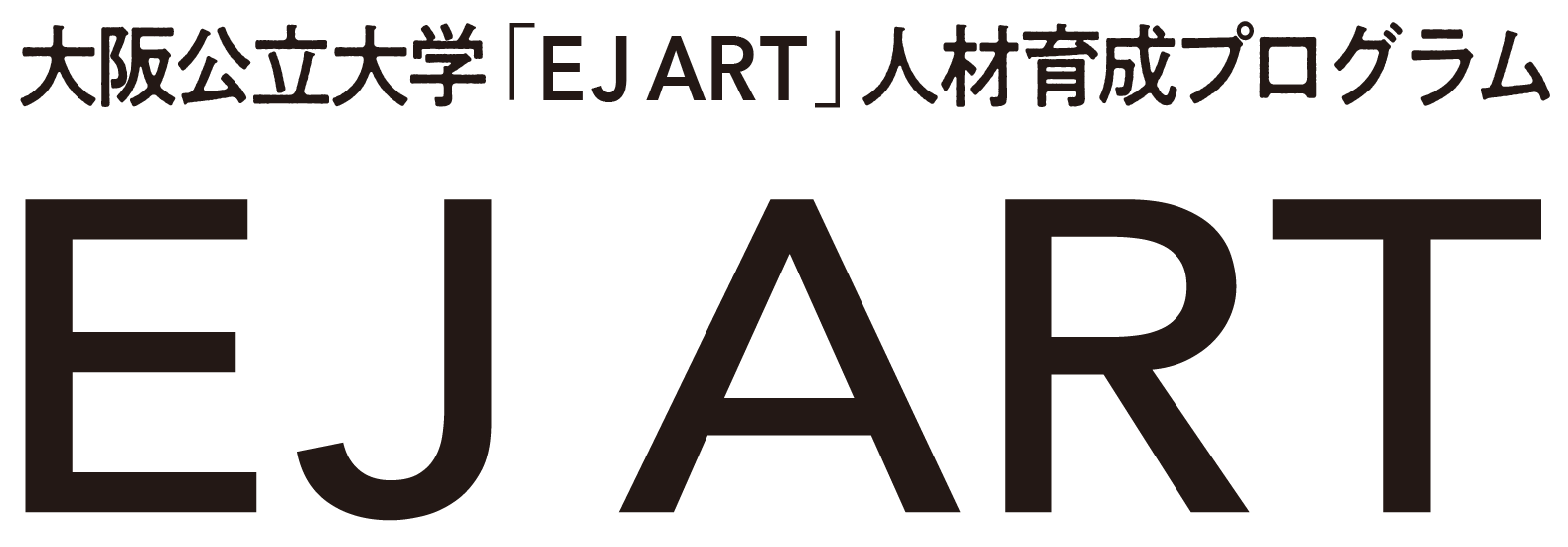社会正義の実現に、美術館や博物館がどのような役割を果たすべきかが問われる中、つなぎ美術館は、水俣病からの地域再生に先駆的に取り組み、地域と連携したアートプロジェクトを展開してきました。本講座では、環境正義といったキーワードを軸に、水俣の取り組みと、公害問題を克服し環境再生を進める大阪・西淀川におけるアートプロジェクトとを対比しながら議論を深めます。
*この講座は、受講生に限らずどなたでご参加いただくことが可能です。
参加費
1回:1,500円/通し:5,000円/学生:1回500円(社会人学生は除く)
*受講生は、公開プログラムの参加費は必要ありません。
お申し込み
*専用応募フォームより開催時間までにお申し込みください。
公開プログラム|応用講座のお申し込みプロフィール

除本理史(よけもとまさふみ)
大阪公立大学大学院経営学研究科教授
大阪公立大学大学院経営学研究科教授。専攻は環境政策論、環境経済学。公害・環境被害の補償と被害地域の再生、原発賠償と福島復興政策、公害経験の継承などについて研究。大学院生時代から大気汚染公害と訴訟後のまちづくりに取り組む。西淀川地域については『西淀川公害の40年』(共編著、ミネルヴァ書房、2013年)を出版しており、あおぞら財団評議員も務める。その他の著書にEnvironmental Pollution and Community Rebuilding in Modern Japan(共編著、Springer、2023年)、『公害の経験を未来につなぐ:教育・フォーラム・アーカイブズを通した公害資料館の挑戦』(共編著、ナカニシヤ出版、2023年)、『「地域の価値」をつくる:倉敷・水島の公害から環境再生へ』(共編著、東信堂、2022年)、『きみのまちに未来はあるか?』(共著、岩波ジュニア新書、2020年)、『公害から福島を考える』(岩波書店、2016年)など。
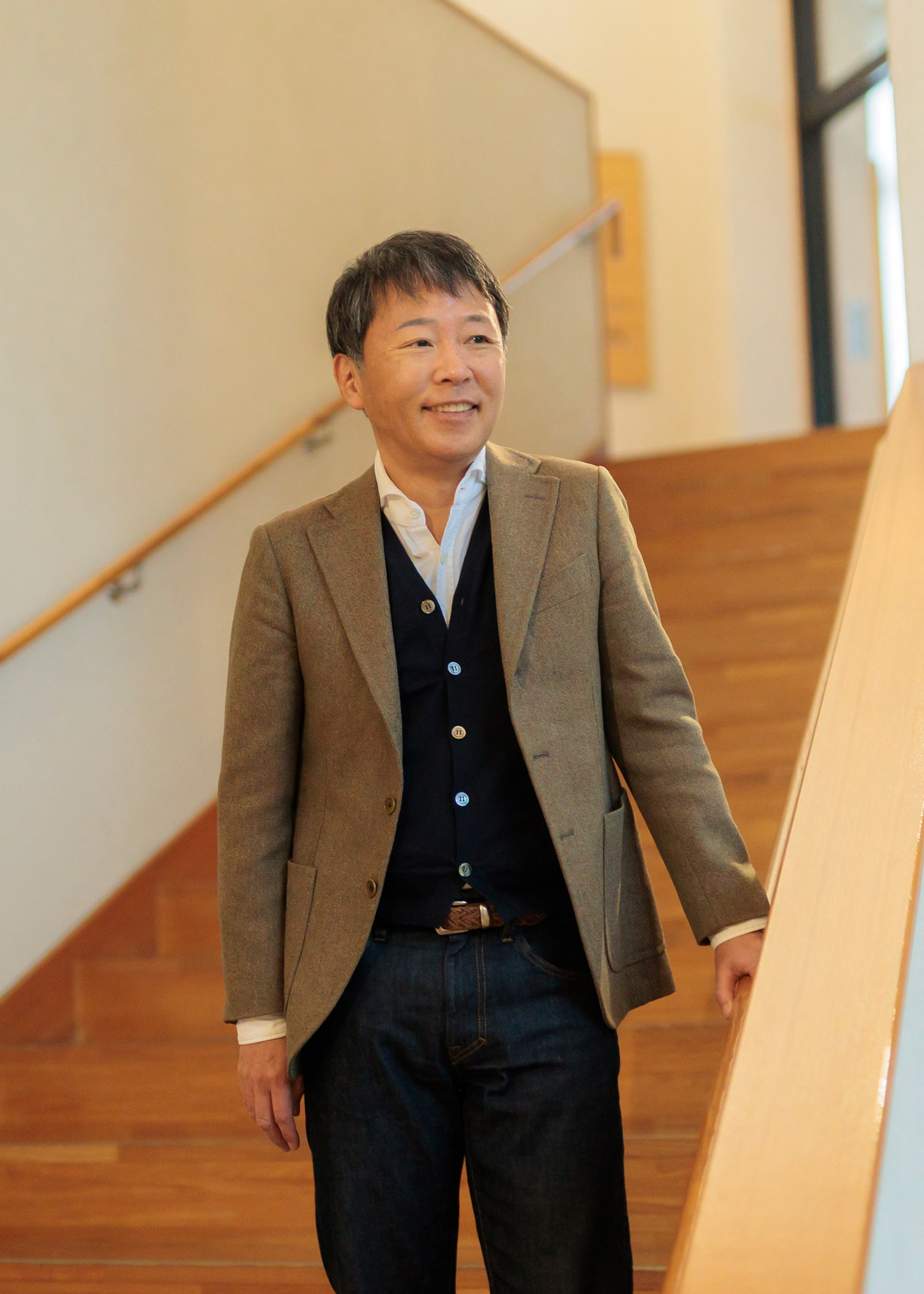
楠本智郎(くすもとともお)
つなぎ美術館 主幹・学芸員
大阪芸術大学芸術計画学科卒業。鹿児島大学大学院人文科学研究科修士課程修了(文化人類学/日本民俗学)。国内外の文化・教育施設等での勤務を経て2001年から現職。各種展覧会を企画し開催するほか、社会教育事業としての住民参画型アートプロジェクト(2008〜)や作品収蔵と個展開催を前提としたレジデンスプログラム「アーティスト・イン・レジデンスつなぎ」(2014〜)を考案し実施している。地域に密着したアートプロジェクトの功罪を問いながら、水俣病の被害地域でもある熊本県津奈木町にて、地方におけるアートと公立美術館の可能性を模索中。佐賀大学非常勤講師(前期)、アール・ブリュットパートナーズ熊本キュレーターほか。
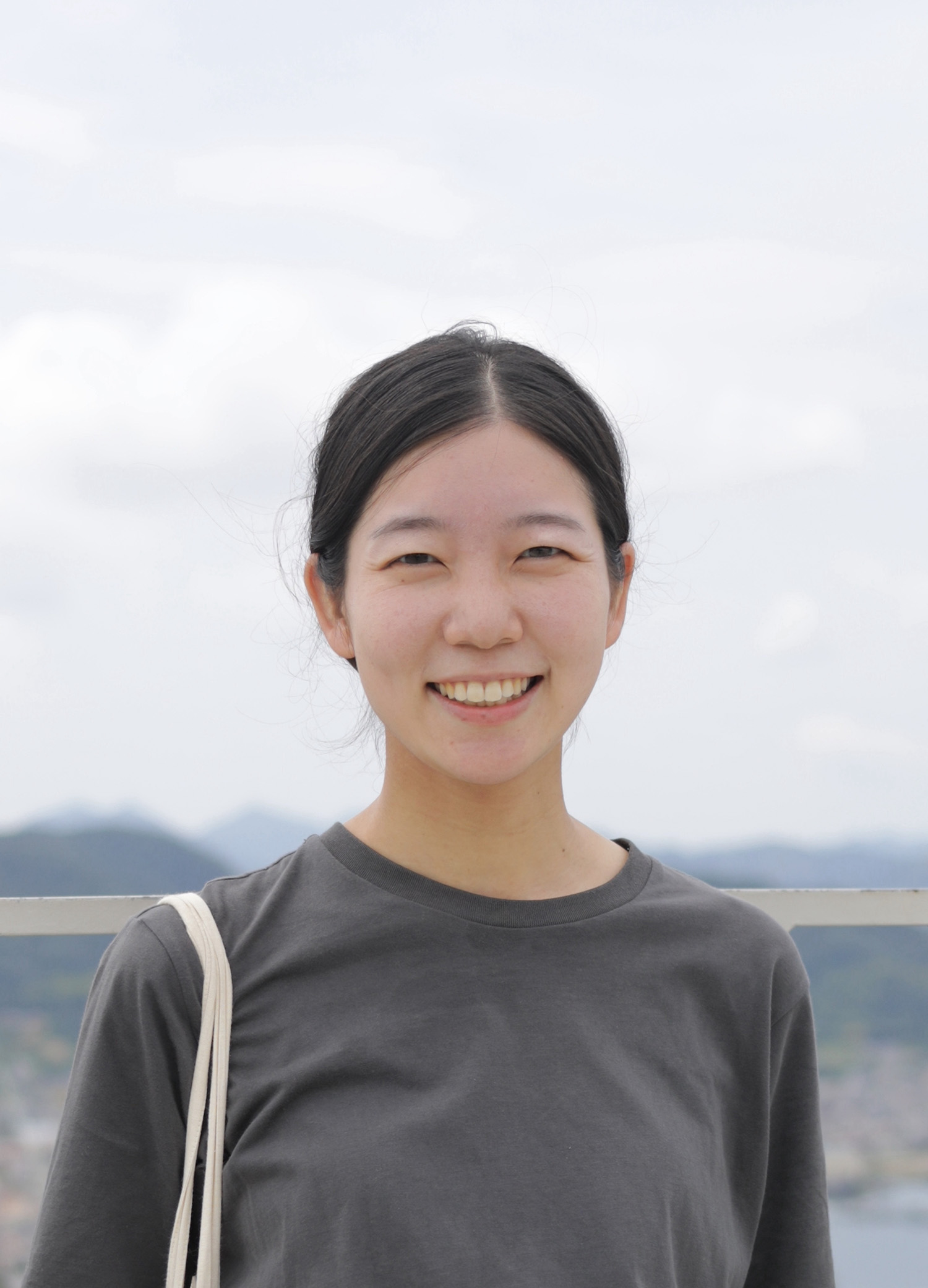
村田のぞみ(むらたのぞみ)
アーティスト
1994年奈良市生まれ。2019年に京都精華大学博士前期過程芸術研究科染織専攻を修了。その場所や個人が持っている記憶に関心を持ち、主に細いステンレス線やテグスを素材として扱い、その場所の物語を紡ぐような作品を制作している。主な展覧会に、瀬戸内国際芸術祭(2022,2019年/高見島)など。

吉田隆之(よしだたかゆき)
大阪公立大学大学院都市経営研究科教授
神戸市生まれ。日本文化政策学会理事。博士(学術)、公共政策修士(専門職)。東京藝術大学大学院音楽研究科博士後期課程音楽文化学専攻芸術環境創造分野修了。愛知県庁在職時にあいちトリエンナーレ2010を担当。研究テーマは、文化政策・アートプロジェクト論。著書に『アートプロジェクトの変貌 理論・実践・社会の交差点』(水曜社、2025年)、『芸術祭と地域づくり “祭り”の受容から自発・協働による固有資源化へ』(水曜社、2019年)、『芸術祭の危機管理-表現の自由を守るマネジメント』(水曜社,2020年)、『文化条例政策とスポーツ条例政策』(吉田勝光との共著、成文堂)ほか。
https://yoshi-lab.org/