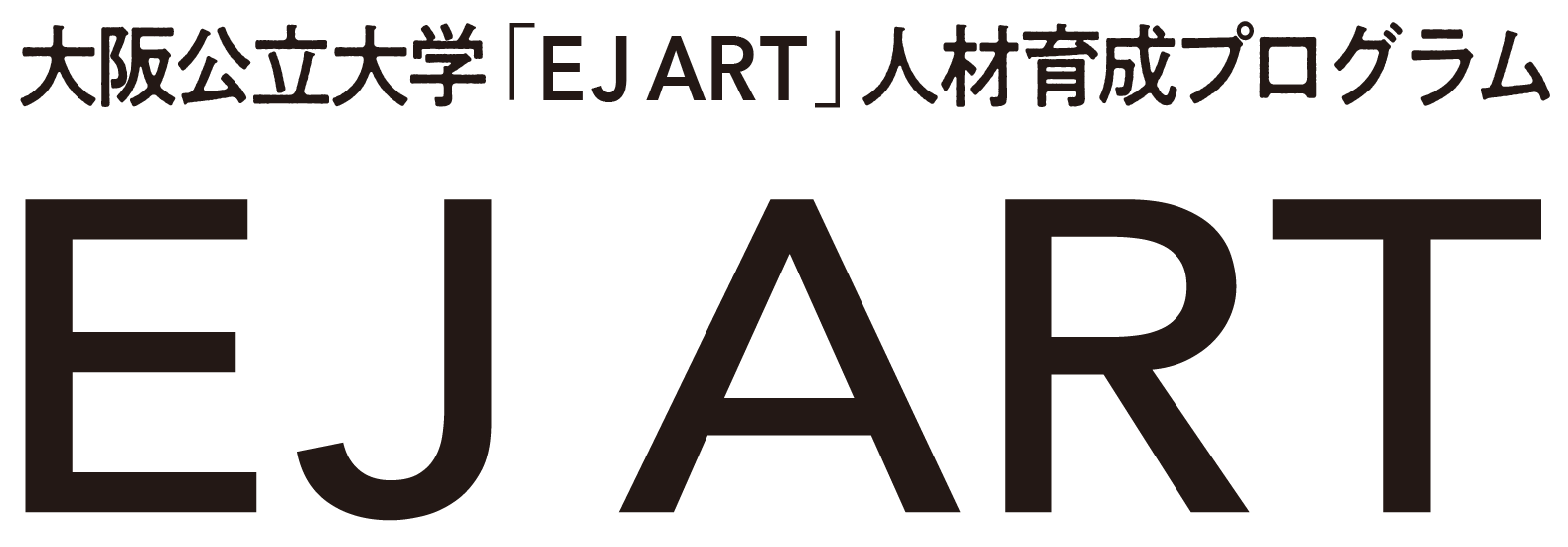「実践・場づくり」の現場で感じた「もやもや」(人々が抱える抑圧や生きづらさ)を見つめ、「ZINE(ジン)」という小冊子や紙面で表現するワークショップを行ないます。なぜ「もやもや」したのか、言葉にして誰かと共有することは、自分や自分を取り巻く社会の認識を批判的に捉えたうえで変えていくことをめざすAOPの第一歩です。
日程
①ZINEについて
日時:10月29日(水) 19:00〜21:00
②ZINEづくりに向けたワークショップ
日時:11月19日(水) 19:00〜21:00
11月20日〜1月20日 各自ZINEづくり
③ZINEお披露目会+ふりかえり
日時:2026年1月21日(水) 19:00〜21:00
プロフィール

撮影:のり やまもと
風間勇助(かざま ゆうすけ)
「アート/ケア/文化政策」研究会、奈良県立大学地域創造学部講師
1991年静岡県生まれ。刑務所とアートを実践、研究しています。この社会で埋もれてしまうかもしれない小さな声に、どのように寄り添い社会に表現としてコミュニケーションを生み出せるのかを考えています。