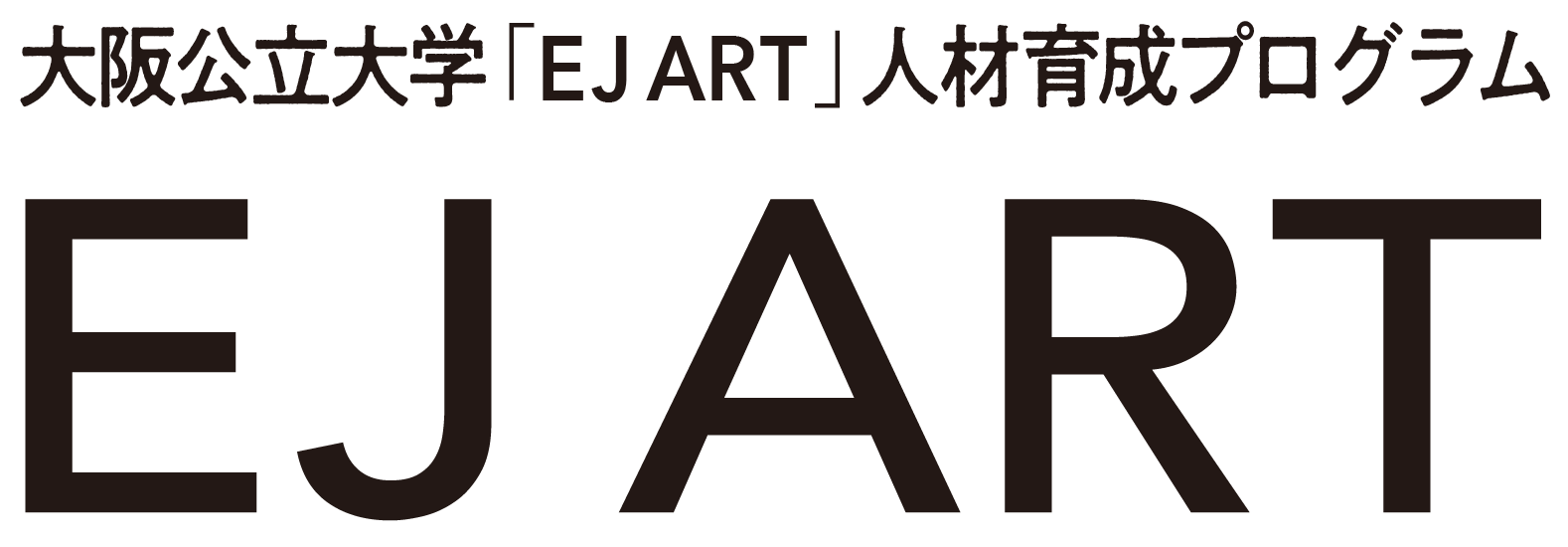竹田恵子氏は、90年代京都における芸術/社会運動に関する研究を出発点に、ジェンダー/セクシュアリティ教育を専門とされ、日本美術界のジェンダー・アンバランスやハラスメント問題の実態調査(アンケート調査・インタビュー調査)などを行ってきました。
EGSA JAPANでは、美術とジェンダーをめぐる教材やハラスメント防止ガイドラインを作成・配布してきました。
本講義では、社会学的アプローチで得た知見をもとに問題提起を行い、参加者それぞれの活動現場や日常ともつながる視点でお話をいただきます。
プロフィール

竹田恵子(たけだけいこ)
東京外国語大学 世界言語社会教育センター講師、EGSA JAPAN代表
東京外国語大学世界言語社会教育センター 専任講師。ジェンダー/セクシュアリティ教育の推進により、芸術創造環境の改善を目指すEGSA JAPAN代表。博士(学術)。
主著に『生きられる「アート」――パフォーマンス・アート《S/N》とアイデンティティ――』(ナカニシヤ出版、2020 年)、『ガールズ・メディア・スタディーズ』(分担執筆、北樹出版、2021 年)、The Dumb Type Reader(分担執筆、Museum Tusculanum Press、2017 年)がある。
アーカイブ
7月17日(水)第二回の基礎講座が開講されました。講師には、東京外国語大学世界言語社会教育センター 専任講師であり、ジェンダー/セクシュアリティ教育と研究を専門とされるEGSA JAPAN代表の竹田恵子さんにご登壇いただきました。
「活動のために活動に燃え尽きないために『無理をしない』」をキーワードにフェミニズムの実践をめざすEGSA JAPANの活動の紹介から講話は始まりました。アンジェラ・マクロビー著「クリエイティブであれ」が引用され、芸術の現場における労働の構造について、社会保障や労働環境の不安定さ、人脈主義、個人的な能力主義、ハラスメント、ポストフェミニズム論(フェミニズムを利用したハラスメント)が紹介されました。芸術をめぐる労働を「労働」として扱う難しさ、会社に所属しにくい働き方と日本の労働基準法の相容れなさ、諸外国のアーティストへの社会保障と日本の差などが語られるなかで、日本の芸術やクリエイティブ産業に従事する人々の立場の弱さを目の当たりにしました。こうした日本全体の社会構造における問題が、クリエイティブ産業に従事するものだけでなく、非正規雇用者全体の問題でもあるとの指摘がありました。
その後、竹田さんが2023年7月から行なっているインタビュー調査の内容が紹介されました。芸術をめぐる労働の現場からの声を知ることで、「これは思い当たる節が自身の働く環境にもあるのでは」と、聞き手がハラスメントのある環境にいたことに気づくきっかけにもなりました。
講演後、6、7人ほどのグループをつくり、講演を聞く中での気づきや疑問などを、自身の置かれた労働環境・社会状況を思い返しながら発言がなされました。それぞれの意見をよく聞き、対話が少しずつ始まり、各グループの議論がつきませんでした。
その後のグループ発表では、竹田さんより丁寧に応答があり、受講生それぞれのプロジェクトを振り返る時間となりました。