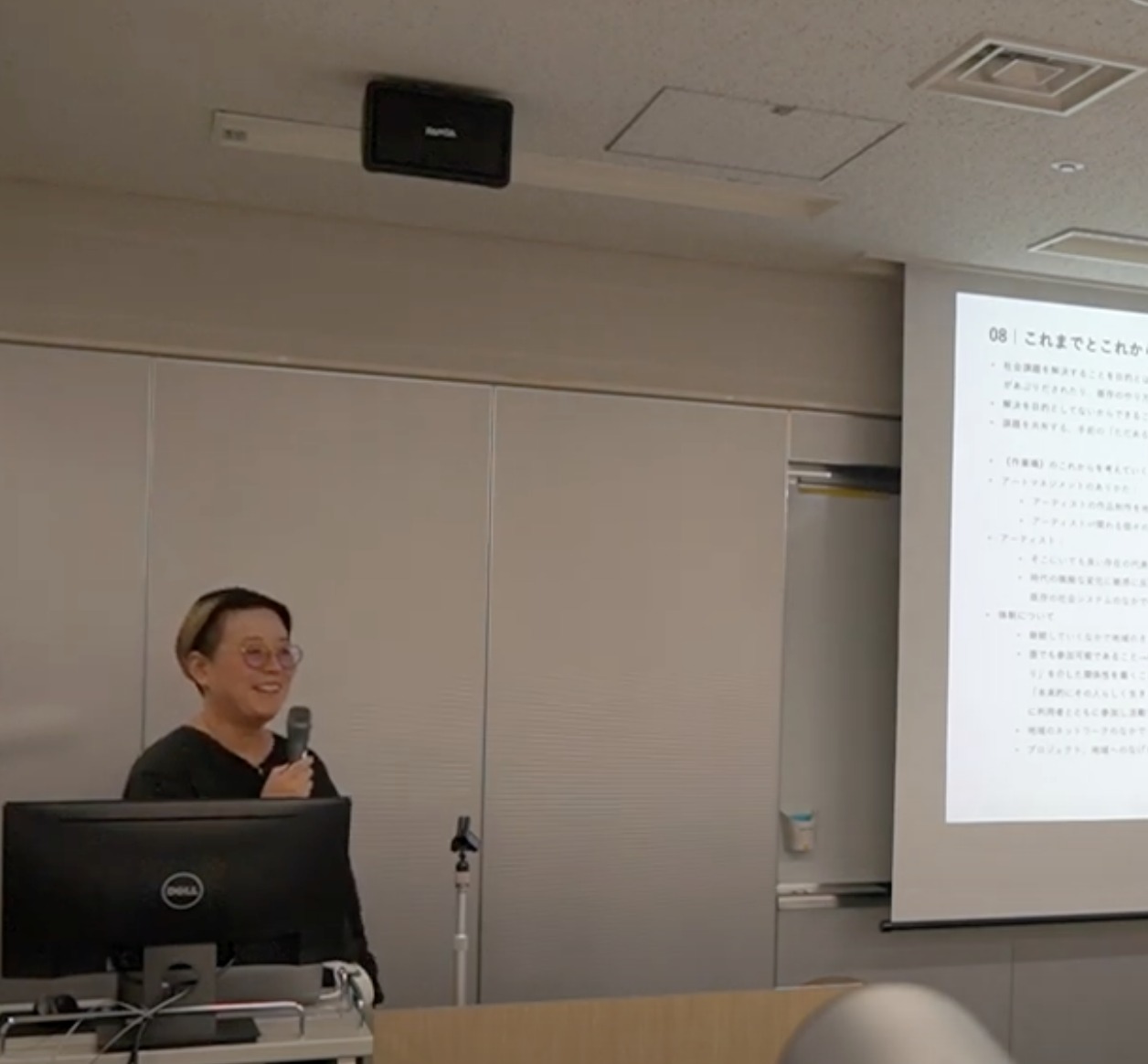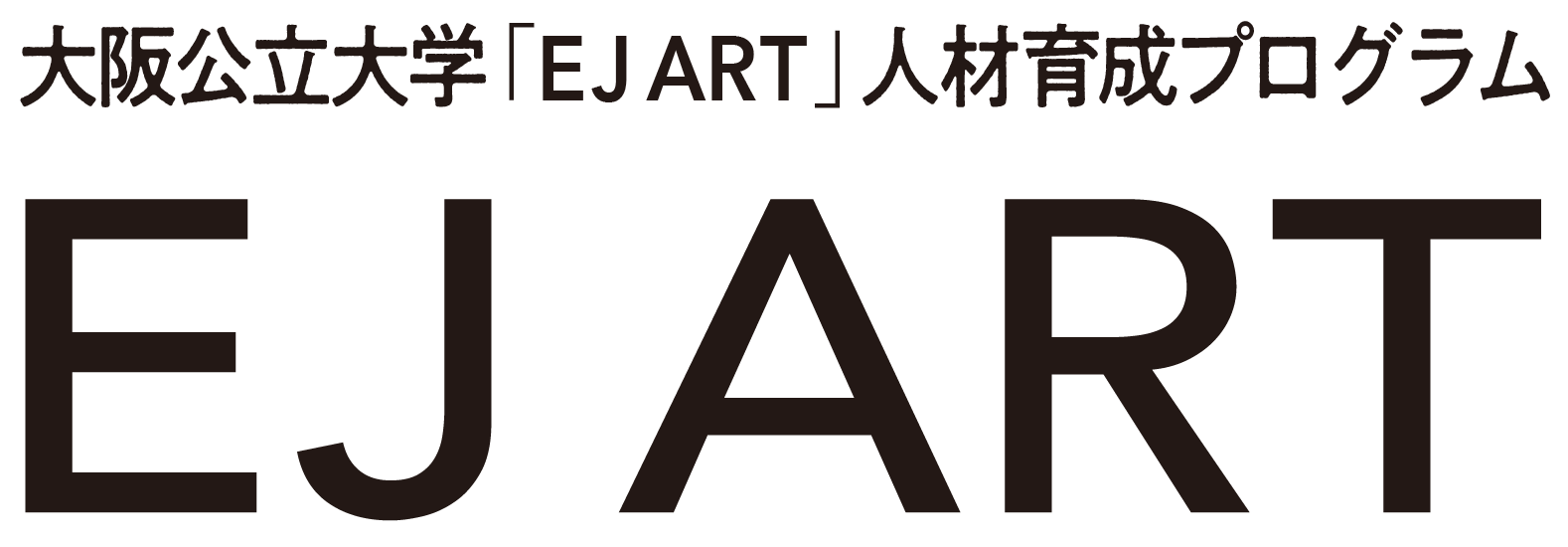2010年代は、芸術祭が流行した時代といえるでしょう。大型芸術祭の一番の課題は、持続可能な財源確保だと考えます。講義の前半では、吉田隆之氏からパンデミック後の日常を取り戻すなかで、財源に折り合いをつけながら、各地域に根差す新たなアートの胎動とその理論的アプローチについてお話します。高岩みのり氏からは、足元の大阪で地域に根差した取り組みとして、西成区のまちをフィールドとした「ちょちょまうヴァナキュラー」を紹介します。後半の皆さんとのディスカッションを通して、ソーシャルアートの未来を現場から紡いでいきます。
プロフィール

吉田隆之(よしだたかゆき)
大阪公立大学大学院都市経営研究科准教授
神戸市生まれ。日本文化政策学会監事。博士(学術)、公共政策修士(専門職)。東京藝術大学大学院音楽研究科博士後期課程音楽文化学専攻芸術環境創造分野修了。愛知県庁在職時にあいちトリエンナーレ2010を担当。研究テーマは、文化政策・アートプロジェクト論。著書に『芸術祭と地域づくり “祭り”の受容から自発・協働による固有資源化へ』(水曜社、2019年)、『芸術祭の危機管理-表現の自由を守るマネジメント』(水曜社,2020年)、『文化条例政策とスポーツ条例政策』(吉田勝光との共著、成文堂)ほか。
https://yoshi-lab.org/

高岩みのり(たかいわみのり)
ちょちょまうヴァナキュラー実行委員会・事務局、一般社団法人brk collective理事、アートマネージャー
1984年生まれ。茨城県出身。2014〜2023年度まで大阪市の文化事業である西成区を拠点としたアートプロジェクト「Breaker Project」事務局スタッフ。現在は、2015年度よりBreaker Projectと美術家・きむらとしろうじんじんが実施してきた「作業場@旧今宮小学校」を軸として2024年度新たにスタートした西成区の事業「ちょちょまうヴァナキュラー」の実行委員会・事務局を務める。多様な地域のアクターと協働し「アート」を媒介とした様々な活動から生まれる出会いやできごとを糧として今日まで活動を継続している。
アーカイブ
8月7日基礎講座5が開講されました。吉田隆之講師と、ちょちょまうヴァナキュラー代表の高岩みのり講師が登壇されました。
はじめに、吉田さんより、本事業の要である、ソーシャルアートの概念と、アートコーディネーターの素養について説明がありました。
ソーシャルアートとは、地域課題に直接的に関わるものでも、既存の回路を利用するものではなく、アートが社会の新しい可能性を開く可能性について目指すものであること、アートコーディネータの素養として、アートが地域の福祉や教育を利用しないような配慮と、不公平さを生じさせないため、社会構造を学ぶ必要があることについて示唆がありました。
つぎに、アートプロジェクトのこれまでのあり方について、大型芸術祭を例に2つ特徴があげられました。
1つめは、「大地の芸術祭」を取り上げ、過疎地域で行われている実験性、偶然性の高い芸術の可能性を地域活性に活用したプロジェクトについて、2つめは、創造都市政策という名目を、わかりやすく市民や行政に見えやすくするために実施される、「横浜トリエンナーレ」「あいちトリエンナーレ」などの都市型芸術祭について紹介がありました。
この大型芸術祭の課題として、予算が大きいため持続可能性の観点から疑問視されていることや、パンデミックを始めとした社会情勢に合わせて運営を組み替えていく柔軟性が求められていることから、自立的かつ持続可能性のあるスモールスケールのプロジェクトの重要性が、語られました。それを受けて、大阪市西成区で活動する「ちょちょまうヴァナキュラー」 事務局の高岩みのり講師へバトンタッチされました。
高岩さんより、「ちょちょまうヴァナキュラー」立ち上げまでの経緯として、2003年にスタートした大阪市の文化事業「ブレーカープロジェクト」の紹介がされ、現在に至るまでの新世界(浪速区)〜西成区を対象としたプロジェクトの広がりが語られました。
アーティスト’きむらとうしろうじんじん’による「野点」(大小2台のリヤカーに、陶芸窯・素焼きのお茶碗・うわぐすりなどの陶芸道具一式と、お抹茶セット一式を積んでまちの様々な場所に あらわれる移動式カフェ – 旅回りのお茶会)が紹介され、コーディネータたちの日々の行動と手腕により、その過程でおきる出来事が誰もが関われるプロジェクトとして地域との関係で往還されていきます。
また、現在廃校となった小学校を舞台に、地域と共有しながら活動する「作業場」というプロジェクトが新たに立ち上がるリアルな活動の様子が話されました。
質疑応答では高岩さんが主に答えられました。「プロジェクトを進めていくなかで、行政からの方針の変化にどのように対応しているのか」という質問に対し、「日々のプロジェクトから立ち上がる状況をスタッフ間で共有し、どのようなことにも答えられる言葉を用意していることが、今に繋がっているのでは」と回答がありました。
また、「『なんかようわからんわ』と、アートに対して言う人と、どのように関わっていますか?」という質問には、「そういうことは常にあることで、いろいろな方向でアプローチをもち、話し続けることが重要」との応答がありました。
ディスカッション後には、「地域の人はいかにして集まるのか、若年層の定着とはどのような状態か」「アートプロジェクトの評価の難しさを、どう言葉にしているか」、「広報はどうされているか、地域外に向けた発信をどうするか」についてなど多くの質問が寄せられました。
高岩さんより、若年層の定着については、「中長期的な関わりを捉え成果としている」、広報については、「それぞれのステイクフォルダーに向け伝えるべき情報を選んでおり、チラシも配布するだけでなく会話をするなど心がけており、新たな団体と協力し広く広報している」などの応答がありました。全体を通して現場の実践・経験を踏まえたからこその受講生との事細かなやりとりができ、多くの実践知を学ぶ貴重な機会となりました。