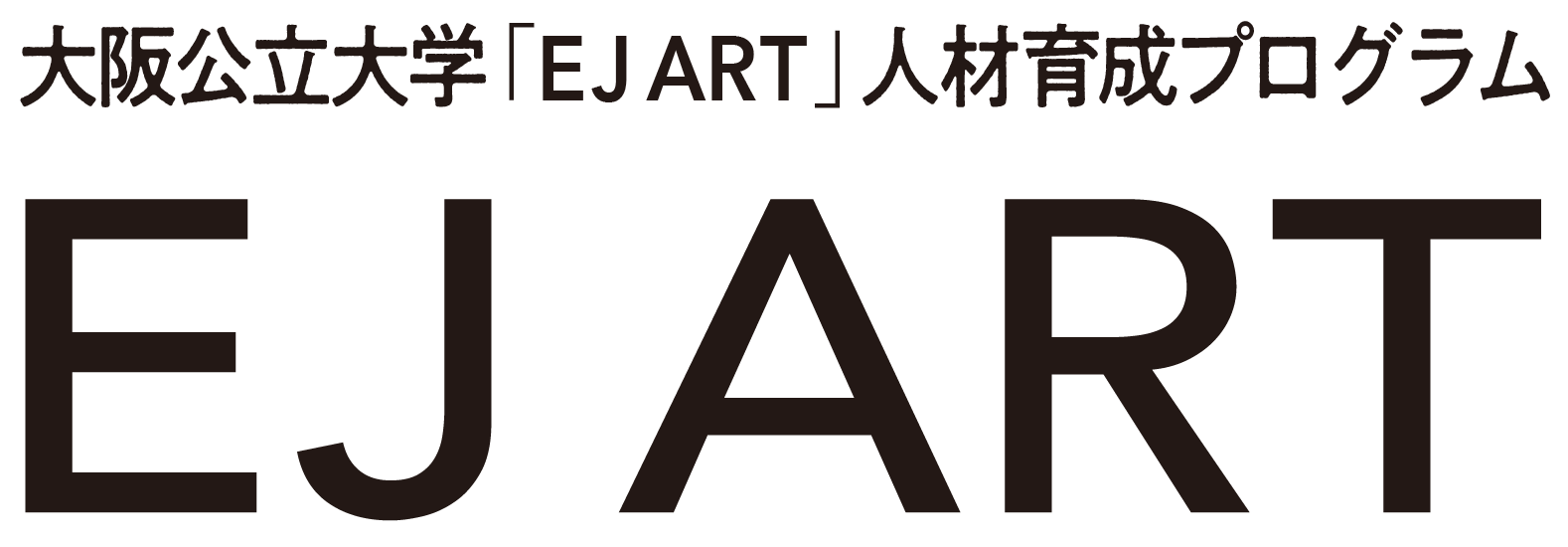中村美亜氏は、これまで特に社会包摂分野の文化事業の評価軸の構築に取り組まれてこられました。
最近では、「芸術文化の価値とはなにか-個人や社会にもたらす変化とその価値」(水曜社,2022)の日本語訳版を刊行され、文化政策分野の評価研究を牽引し、活躍されています。
本講義では、学会の最先端の議論を紹介するとともに、ワークショップを取り入れながら、評価の意義や重要性を自分ごとして体感していただきます。
プロフィール

中村美亜(なかむらみあ)
九州大学大学院芸術工学研究院教授
専門は文化政策・アートマネジメント研究。芸術が人や社会に変化をもたらすプロセスや仕組み、それを踏まえた文化事業の評価に関する研究を行なっている。訳書に『芸術文化の価値とは何か』(水曜社、2022年)、編著に『文化事業の評価ハンドブック』(水曜社、2021年)、単著に『音楽をひらく』(水声社、2013年)など。ジェンダー/セクシュアリティなど多様性・包摂性に関する著作も多い。日本文化政策学会、アートミーツケア学会理事。日本評価学会認定評価士。
アーカイブ
8月21日(水)基礎講座6では、これまで特に社会包摂分野の文化事業の支援や評価に取り組まれてこられてきた、九州大学大学院芸術工学研究院の中村美亜教授が登壇されました。
最初に「評価とはなにか」についての説明がありました。評価とは、「事実特定と価値判断からなる」ものであり、それにより「価値が引き出される」ことであると定義の紹介があり、文化事業と評価のあり方について、大きく2つの例をあげられました。
1つ目に、文化事業を成果につなげるには、計画通りに設定したゴールに達成しようとするのではなく、様々な出会いや変化を受け止めつつ、臨機応変に形成的評価(プロセス評価)を行いながら進めていくが肝心である。また、総括的評価(アウトカム評価)を行う際には、誰のために評価をするのかを見定めなければならない。
2つ目に、経済効果や福祉、教育の課題解決を基準に文化事業の評価を得ようとしたり、文化芸術だけで課題解決をはかろうとすることは難しい。
評価では、そこにある人間活動の総合依存関係の変化や成長をみるべきである。文化事業の価値として、人間の意識や地域の「変化を生み出す状況」を作り出せたかを評価する必要があると示唆されました。
質疑応答では、「事業を評価する際のポイントは何か」、「定量評価は必要か」、「客観的評価とはどのようなことか」などの質問がありました。中村さんより、「事業を評価する際には、活動内容を評価することに目がいきがちだが、それ以前に、プログラムセオリー(事業設計)がうまくできているかを検証することが重要であり、何を目指し誰のために行うのかを整理してから、活動内容を検証しなければならない」、「定量(量的)評価と定性(質的)評価のどちらも必要で、事業者が自ら評価されるべきポイントを見つけだし、適切な方法を使って強みを見せる必要がある」、「評価は事実特定と価値判断からなっているので、変化を示すエビデンス(事実特定)を示す必要がある。表情、行動、言動などを注意して観察し、記録をとっておくことが大切である」などの応答がありました。
休憩後、「公正と正義を基軸とした文化事業を1年展開するプログラムを企画する」をテーマに、ロジックモデル作成のグループワークを行いました。
グループ内の現場を持つ受講生の現状を共有したのち、理想のプロジェクトの最終アウトカム、中間アウトカムを明確にしながら、ディスカッションを通して事業設計を行いました。
ワークの途中では、中村さんより「アウトカムをイメージするときに、主語を大切に考えるように」などとのアドバイスがあり、グループ内での話し合いが途切れることなく活発に進んでいきました。白熱した話し合いに、前のめりになりながら頭を突き合わせ話す姿が見られました。
グループワーク終了後、2つのグループよりプロジェクトのロジックモデルの発表がされました。1つ目のグループは子ども食堂でのアートプロジェクトがテーマで、様々な人々のつながりつくっていく段階について話されました。2つ目のグループは展覧会の企画がテーマで、社会平和と多様性のある社会へ貢献するための工夫にについて共有されました。
中村さんより、「誰もがイメージを共有できる目標設定が言語化されているところがよい」、「誰に向けて事業を行うかを含め、多様な人を思い浮かべながら考えられている。現状では不足している活動についても気づいたところが素晴らしい」などの講評がありました。
今回の講座では、受講生は自身のプロジェクトの、まだ見えていない強みや価値の発見ための評価の考えやメソッドを学びました。